朱子學では「事物には皆その在り方を規定する理があり、その事物の理を窮め知ること」を窮理と言ふ。そして「理を窮めるには『一木一草』の理に至るまでいちいち全部知り盡くす必要があるが、さういふ努力を積み重ねれば、或る段階で『豁然(かつぜん)貫通』して、すべての理を一擧に了解し得る」ものとした。
この小欄が、文字文化の「一木一草」たらんことを祈る。
『エスター・ローヅの講演より』
谷田貝常夫
エスター・ローヅ先生の声がここから
1 校友會歡迎會にて(昭和52年最後の来日時に、於東京プリンスホテル)
『手書き文字と「漢字テストの不思議」』
黒田信二郎
常用漢字の「『手書き文字の字形』と『印刷文字の字形』に関する指針」
文化庁が、常用漢字の「『手書き文字の字形』と『印刷文字の字形』に関する指針」をまとめて、公開するという。文化庁の会議資料にはその目的として「漢字の形状における細部の差異にまで必要以上に注意が向けられ、それが正誤の基準とされたり、手書き文字と印刷文字の習慣が理解されず、どちらかの字形を誤りとみなす状況」があり、「とめるか、はねるか、はらうかなどにこだわらない多様な字形を認めるべき」という指針を示そうというものだ。
公表されている「常用漢字表」(平成22年内閣告示)には、「付」として「情報機器に搭載されている印刷文字字体の関係で、本表の通用字体とは異なる字体(通用字体の『頰・賭・![]() 』)に対する『頬・
』)に対する『頬・![]() ・剥』など)を使用することは差支えない」とし、「明朝体と筆写の楷書との関係について」その違いを具体的に示して解説している。しかし、教育現場には充分浸透しておらず、学校の先生方も生徒や保護者の「クレーム」に対応せざるを得ないため「教育指導要領」という「マニュアル依存」に陥る状況があるらしい。
・剥』など)を使用することは差支えない」とし、「明朝体と筆写の楷書との関係について」その違いを具体的に示して解説している。しかし、教育現場には充分浸透しておらず、学校の先生方も生徒や保護者の「クレーム」に対応せざるを得ないため「教育指導要領」という「マニュアル依存」に陥る状況があるらしい。
教育現場の漢字指導と入学試験
特に教育現場での「入学試験」対策は大学を頂点に、高校、中学と下へ下へと影響が連鎖していて、「正しい書き方」を強制し、高校、中学校、小学校の現場に及ぶ。「漢字」そのものを書かせる出題はもちろん、今後「記述式問題が思考論理力をみるために重要である」としてその方針が強化されると、答案に書かれた文字の正誤がますます採点に影響するようになり、現場では「判読できれば良いのか、文字が違っているから零点、あるいは減点か」という判断のむずかしさが生じる。1点差で泣くかもしれない受験生にとってみれば深刻な問題であり、「多様性」とか「許容」とか言われても、皆が納得できる基準が求められるのも無理はない。文化庁の新指針はその反映ともいえよう。大学入試のセンター試験も2020年度から、従来の選択式に記述式の問題を追加する方向で、文部科学省の専門家会議が問題例を公表した。 記述式は国語と数学から導入し、最大300字程度。採点に時間がかかるため、マークシート方式とは日程を分離し、前倒しも検討するという。
この問題を取り上げたのが、もう10年前のことだが「東京ビデオフェスティバル2007」の大賞受賞作品、長野県梓川高校放送部制作『「漢字テスト」の不思議』で、その解説によれば「小中高200名の先生による漢字テストの採点のバラツキや基準の曖昧さに着目し、要因を解明する行動の取材記録。教育委員会、文化庁などの関係部門に基準はなく、入試基準か先生のこだわりなのか。様々な発見や矛盾を高校生が明らかにしていく」内容である。学校の先生をはじめ、県教育委員会、文化庁国語課、さらには漢字検定協会にまで取材に行き、「先生! IT時代の漢字テストを考えてください」と訴える約20分の作品であるが、大変良くできていると思う。
文字コードポイントと対応フォントとしての「保」
このビデオ作品にも例として出てくるのが「保」である。常用漢字表の解説では、いろいろな書き方がある「つけるか、はなすかに関する例」として「保」(木)でも「![]() (『玉篇』典拠)」(ホ)でも差支えないとしている。
(『玉篇』典拠)」(ホ)でも差支えないとしている。
「保」と「![]() 」はJIS漢字でもUnicodeでも包摂され、UnicodeのIVSでも字形の切り分け対象とはなっていない。一方、学校の現場では教科書にある「保」を唯一正しいものとして扱うケースがあるらしい。
」はJIS漢字でもUnicodeでも包摂され、UnicodeのIVSでも字形の切り分け対象とはなっていない。一方、学校の現場では教科書にある「保」を唯一正しいものとして扱うケースがあるらしい。
『今昔文字鏡』によれば、「保」「![]() 」には、大漢和辞典に収載の姿形書換字である
」には、大漢和辞典に収載の姿形書換字である![]() 、
、![]() のほかに関連する同字、古字として
のほかに関連する同字、古字として![]() 、
、![]() 、
、![]() などがあげられている。
などがあげられている。
2000年に及ぶ手書き文字の歴史から見ると、コンピュータによる漢字処理が可能となってわずか50年である。印刷文字の「明朝体」は明代以降にまず中国で、後に日本でも、手書きの楷書を印刷用の板木に彫刻するための書体として生まれたもので、印刷業の発展とともに活字となり、フォントとなった。このように手書きの「楷書体」と活字の「明朝体」は発展の過程が異なり、それぞれに独自の特徴や習慣があるため、両者の間で字形に違いが見られる場合も少なくない。
「外字」は活字印刷になってから「活字ケース棚(通称「馬」)」の棚外として生まれた概念であるが、コンピュータ処理になってさらに「文字コード外」と「端末機器フォント実装外」の二つの概念に切り分けられるようになった。
青天井の文字表現をIT社会の日常的な使いやすさにどうつなげるか、文字の多様性にまつわるコードポイントと対応フォント字形についての課題は尽きない。文字文化協會が進めている『漢字基本図形表』の試みもこの課題に取り組むものだが、むしろ50年後、100年後には、ITやAIの進歩により、人間本来が持っている「文字判読能力のあいまい図形認識」という側面からの、新しい技術的なアプローチがでてきているかもしれない。
『世界村の中の日本語「文字村」とその意義』
長村 玄
80年代から90年代には、よく海外に出かけた。当時のソウル金浦空港では明らかにキムチの臭いがしたし、香港や台北、クアラルンプールの空港でも特有の臭いがしみ込んでいて、いやが上にも外国に来たという実感を味わった。しかしそこに着いたときに孤独感や自分が場違いな人間だといった感じを持ったことは一度もない。ところが外国人が日本に来ると、かなり違和感を持つらしい。古田暁は『異文化コミュニケーション』(有斐閣選書)のプロローグでつぎのように述べている。
ニューヨークの空港に着くと、人は自由の空気に触れる思いがするといわれるが、成田空港ではそのような空気は感じられず、彼らがよくいうように、息づまる思いがするのである。東京人が丹波の村に入るようなもので、つねに異質な存在として四方から凝視され、まるで動物園の檻の中にいるように感じてしまう。
また、
国家は表層で生き、文化は深層で息づいている。国家は意識的に保たれるものだが、文化はほとんど呼吸と同じように意識されないから文化だとさえいえる。(中略)ところが日本の場合、この国家と文化との乖離がはなはだ小さい。
とも指摘している。
日本は国家と文化との乖離が小さいから、ほんらい深層に息づくはずの文化が表に出やすく、それを当たり前のように、いわば空気のように受け止めて暮らしているのがわれわれ日本人であるとも言えよう。それは文字についても同じである。
言語は文化である。この点を忘れて文字の国際標準化を推し進めれば、かならず固有の文化が損なわれる。文化という視点で見れば、同じ漢字を使う国であっても中国と日本はまったく異なる環境にある。多様性にこそ文化の本質があることを忘れてはならない。
外国人が成田で違和感を感じる構造があることの裏返しとして、諸外国のルールをそのまま文字の規格に当てはめてしまうことは、日本の文化を浸食することになりかねない。これを十分に踏まえた上でなければ標準化などできないのだが、現実には浸食が進んでいる。それでは文字について鎖国政策を採るべきであろうか。そうはいかないし、また、それでは現今のグローバル化に逆行することになり、ひいては世界から見放されるであろう。もちろん諸外国との情報交換もままならなくなる。マクルーハンの言う「世界村」は、すでに現実の姿なのであるから。
外国人が日本に一種の壁を感じるように、日本人が文化的視点で文字の規格・標準をみると、そこに壁を感じる人も多いはずだ。現在の標準化が文化的視点を欠いているのは紛れもない事実である。国家という表層で機能するところでは、できるだけ壁をなくすべきだが、深層に息づく部分にまで同じ構図を持ち込んではならない。たまたま日本という国は深層にあるべきものが表層にあらわれ、それがひとつの世界観を形成してきた。文字・コトバは、まさにその中核に位置する。
それでは何が壁になっているのであろうか。
もともと日本人は文字を持っておらず、漢字の音を充てて表現した。万葉仮名である。したがって同じ音に対して当てはめる漢字が違うということが常に起きる。かくして、海に生きる人たち「アズミ(族)」は、阿曇、安曇、厚見、厚海、渥美、阿積などという表記の種類を生み、耕地や小集落を意味する「カイト」は垣内、街道、海道、開戸、皆渡などという地名を生んだ(谷川健一『日本の地名』)が、このような例を具に見ていけばある地域でだけ使われる地域文字にも出会う。これらを「標準の字体」で表記することが正しいことであろうか。否、である。地域文字にこそ歴史がしみ込んでいるからである。
漢字使用の実態は、コードに載っているとか漢和辞典に収載されているといった規範の中で議論できるものではない。笹原宏之は『現代日本の異体字』の中で、つぎのように述べる(同書第2章「異体字の使用状況とその背景」)。
現在、日本で実際に使われている漢字は、どのような字体のものなのであろうか。その答えは、漢和辞典を開いても導き出せない。国語辞典にも、表記辞典にも見いだすことは難しい。
こうした背景を強く認識し合うことが大切である。多くの文章において位相文字や地域文字の使用が必要になる場面がある。芭蕉は“禅”の旁をツ+日+十と書いたようであるが、これは芭蕉の癖字ではなく、『冬の日』『猿蓑』『風俗文選』『葛の松原』にみられる、ごく普通の書き方の一つであるらしい(山本唯一『芭蕉の文墨 -その真偽-』思文閣出版 1997)。このような文字の字体を「そのまま」記したいという要求は当然のものだが、だからといってユニコードに収載するものでもあるまい。しかし使ってはならないということにはならない。規格がそのようなシバリを強要する立場にはなく、規格より表現の自由が優先されるべきことは法的に見ても明らかである。 地域文字のほとんどは漢和辞典にも載っていない。これらの文字にコードを振るなどというのは馬鹿げているが、それでも必要なのである。一方、現在の規格は強引に標準に寄せることを狙っているように見える。
笹原宏之は岩波新書『日本の漢字』において、“編輯者、校正者、そして著者までが「統一病」に罹ることがある”と述べているが、まさにこのことを指しているのであろう。統一病に対して「同字病」というのがあって、平安時代から、和歌や連歌などでは一首の上の句と下の句とで同一発音の語・文字の重出を欠点として避ける決まりさえもあった、と同書の中で述べられているが、「中身」さえ伝わればよいという情報交換ならいざ知らず、歴史記述などにおいてはJISやユニコードの範囲で、などという制限はあってはならないのである。そのことが、とくにコード推進主義者たちにはわかっていない。
もうひとつ『日本の漢字』から引用する。“「死んだ正しい文字」より「生きた俗字略字」の方が、文字としては価値がある”と述べているが、その通りである。標準化の第一に掲げる基準は「それが正しいものである」ということであるが、文字というのは、そんなに簡単に「正しさ」を決めることはできないし、決めたところで、それに従わなければならないものでもない。文字に関しては「もっと自由を」と叫ばざるを得ない。
文化という視点を踏まえつつ実運用の便を考慮すれば、文字コード体系を補完する仕掛けが必須である。それがないかぎり日本語「文字村」は消滅するであろう。そしてそれは日本文化の死をも意味する。
【本稿は著者の許諾を得て、『外字異体字のバリアフリーを目指して』(文字文化協會刊)より転載した】
『梵字の五十音図』
谷田貝常夫
梵字では日本人にとって大切なことがある。私たちは今、名簿の並び順なり字書の単語の並べ方をアイウエオ順にしているが、この順序やそれに基づく五十音図が実は梵語から来ているのである。
聖徳太子が随に派遣した使節の小野妹子が持帰ってきたものに「貝葉(ばいよう)梵本」と呼ばれる教典がある。これは椰子などの樹木の葉や木片を今の紙の代りとして文字を書いたもので、仏教教典はその貝葉に梵字(サンスクリット)で書かれた。中には五十の字母を配列したところも見られる。この小野妹子が西紀605年にもたらした、世界最古の梵字資科とされる『法隆寺貝葉梵本』は、今、東京の国立博物館で見ることができる。このことからも、日本ではかなり古くから梵字を目にしていたことは確実である。
江戸時代前期に、契沖という梵字の勉強もし日本の古典も広範に読んでいた真言宗の僧が、縁あって水戸光圀の依頼を受け、万葉集の注釈をしたものが『万葉代匠記』という本だが、契沖はその時の研究から音図を作り、それに「五十音図」という名前をつけた。それには、アイウエオと共に新しく作った字を示しているが、それは母音アイウエオと子音を組合わせたもので、今でいうローマ字表記と同じ考え方をしている。

(注)梵字図形の下の番号は文字鏡図形番号を表わす
子音をまず置き、その下に母音の略字をもってきて一字としている。例えば、[キ]は、「加」の下にイにあたる「以」、その略した「人」を置いて[
その他幾つかを挙げるので、上の表と見比べてみられたい。
(ス=
子音発音記号の無い日本においての、契沖の涙ぐましい努力には頭が下がると共に、このような梵字の研究、応用から、近代的な国語学が生まれてきたことに私たちは気づかされる。
【本稿は著者の許諾を得て、『外字異体字のバリアフリーを目指して』(文字文化協會刊)より転載した】
『編集傍訊―異體字整理って何?(3)』――「新字」「舊字」を確かめる
高崎一郎
さて、「活字體」と「筆記體」、「異體字の意味」と話を進めてきましたが、もうひとつ 「新字」「舊字」があります。
「新字」「舊字」 はあまり適切な用語ではないのですが、他によい言葉もないので仕方なく使ひます。「新字」でない「略字」はいくらでもありますし、「康煕字典體」の意味は嚴密すぎます。かといって「いはゆる康煕字典體」では冗長ですね。「正字」は價値觀の問題が入りますので混亂しがち。「基本字」としたいところですが、殘念ながらあまり普及してをりません。
もっとも「新字」の字種や字體は年代と共に大いに變化しますし、「舊字」だって辭書によって少なからず異同があります。嚴密な考察ですと「○○年の内閣告示によると」などと根據が必要なのでせうが、本稿ではむしろ「新字的なもの」「舊字的なもの」の性格を大づかみに理解してもらふ事を優先してゐます。
「新字」を確かめるには、どうしたらよいのでせう。端的には「最新の漢和字典を見ればよい」のです。何か新しい國語施策が發表されると、辭書もすぐに「新基準に全面準據」などと帶つきで改定版が賣出されます。もし自分で調べようとして原典にあたると結構面倒です。といふのも
・『当用漢字表』や『常用漢字表』
・『表外漢字字體表』
・『同音の漢字による書きかえ』
・法務省の人名漢字
・JIS漢字コード規格票
など、比較參照すべき資料はかなりの量にのぼります。
「新字」の字體を分析するのであれば、『常用漢字表』だけでほぼ十分です。なぜなら表にない漢字であっても略しかたは延長線上にあるからです。唯一の例外として、「姬」が「姫」になったのに「煕」の「𦣝」が「臣」でなく「熙」となりました。
では次に「舊字」を確かめるには、どうしたらよいのでせう。もちろんこれも漢和字典を見ればよいのです。中型以上であれば必ず「国の旧字は國」などと大きな表示がある筈です。『常用漢字表』にも參考として括弧つきで康煕字典體を示してゐますが、細部まで網羅したものではありません。
「舊字」すなはち「康煕字典體」ではありません。『康煕字典』だっていろいろ誤りがあります。いやむしろ誤りや矛盾が多い辭書と批判されてもゐます。ですから「康煕字典體」と限定すると、思はぬ誤りを抱込む危險が大きく、また昔の漢和字典といへどそんなに嚴密に編輯してゐるわけではありません。もちろん康煕字典の精神は大いに受繼ぎ、時に明らかな誤りを正す事もありますので、學術的には「いはゆる康煕字典體」と稱される事が多いやうです。
「舊字」については、 堅苦しい勉強をするのもよいですが、戰前の出版物に親しみ雰圍氣をつかむのも大切でせう。古本屋でごく安手の、できれば總ルビつきの端本でよいのです。近年は圖書館がネット上で所藏文獻を積極的に公開し始めましたから、むしろそちらの方が早いかもしれません。
「國立國會圖書館デジタルコレクション」、 「近代デジタルライブラリー」あたりが充實してゐます。
辭書の編輯は文化的にとても意義ある事業です。たとへ常用漢字表が日本國としての規範であったとしても、同時に「舊字」をより矛盾ないものにする努力も續けられてゐます。ですから「いろいろ漢和字典に親しみ、できれば比較してみてください」と聲を大にして申上げます。
『編集傍訊―異體字整理って何?(2)』――「標準的ならざる字體」が異体字
高崎一郎
皆樣は自分が日常讀み書きしてゐる漢字が戰後大きく變った事をご存じでせうし、またそれ以前の「舊字」も何となく讀める事でせう。
・昔の人は「學」とか「藝」とか難しい漢字をよく書けたものだ。
・たまに昔の字にこだはる人もゐるけれど、俺には關係ないな。
といったあたりが「常識」でありませうか。
平成十二年に文化廳から『表外漢字字体表』が發表されました。これによって「舊字」は公的に「舊字」ではなくなり、『常用漢字表』と併せて二種類の異なる文字設計が同居するといふ、靜かながら政策の大轉換がありました。
「学」「芸」を「學」「藝」に戻したわけではありません。しかしより使用頻度の少ない字。たとへば「波濤」や「範疇」などを「涛」「畴」と略していいぢゃないかといふ意見が正式に否定されたのです。もともと「濤」「疇」のやうな「難しい字」は廢止すべきものであり、國語政策としては關知するところではないといふ見解だったわけです。
ですから今後は「壽」「學」「藝」などについても「俺には關係ないな」といふ状況ではなくなったと言へます。「濤」は常用漢字表に入ってゐたかな、もし入ってゐないのなら「涛」と書いてはいけなかったかな、いやまてよ『表外漢字字体表』では許容字だった筈だな、などと氣を遣ふのはじつにつまらないですね。ぜひ系統的に理解してゆきませう。まず、面倒なやうですが、言葉の意味だけ確かめておきます。
「異體字」とは同音同義で形だけ異る漢字を指します。典型的な例では「國・国・圀」はそれぞれ異體字の關係にあり、「邦」はさうでないとされます。訓こそ同じ「くに」であっても、字音「コク(國)」と「ハウ(邦)」が異りますので、同一視はできないのです。
しかし一般的に「異體字」は「標準的ならざる字體」といふ意味で使ふ事が多いやうです。昔は「國」が標準で、これに對する「国」や「圀」が異體字、その後「国」が正式の字となったから、現在では「國」「邦」が異體字といふ評價です。場合によっては「国」が「新字」、「國」は「舊字」、「邦」のみ「異體字」とする事もあります。
一寸とうるさい樣ですが、後者ですと「どの字が標準か」といふ價値判斷が加はり、説明がややこしくなるので、「異體字」を前者の意味とするほうが、判りやすいと思ふのですが、如何なものでせうか。
『反訓といふもの 』
谷田貝常夫
厖大な數の漢字にはいつも目眩ひを感じるほどで、やたらに辭書を引いてきましたが、時折、不思議に思ふことがありました。一字で正反對の意味があつたりするのです。
例へば[離]は、離反とか離思など「はなれる」とか「別れる」の意だと思ひ込んでゐましたが、同時に「連なる」とか「付く」といふ意味もあるのです。[雛]はひよこのやうに小さい鳥と信じてゐましたが、「おほとり」とも書いてあります。雰圍氣の[雰]には「めでたい氣」といふ意味の一方で「雰氣」となると「わるい氣」とあります。そのやうなことから折々に目を凝らすと、[躋]は「のぼる」と「おちる」が出てくるといつた反對の意味があるといふ現象に興味をそそられました。
もつとも文章の中で見つけたことではないので、いはゆる西歐の「反語・アイロニー」の定義のやうな「ことさらに《ばれるやうに》につく嘘」といつた實感は感じられないにしても、言語のこのやうな在り方にひきつけられました。反語はすでに古代ギリシャで意識され、ソクラテスの話術がその典型とされてゐます。この「ソクラテス的反語」については畏友佐藤信夫の説明を引用しませう。「ソクラテスは無知をよそほつて人に教へを請ひ、いろいろ質問をかさね、さて氣がついてみたら、いつの間にかその相手の無知が露顯してゐる、といふ筋書きである」
このやうな漢字の反語的現象の話をしたら、高崎一郎氏からそれは「反訓」といふものだと教へられ、遂には『古漢語字義反訓探微』といふ台灣出版の本まで見せてもらふまでになりました。この語、大漢和辭典にも出てゐました。「文字の本義の一半を存し、しかも他の意味に轉じたのではなくて、全然反對の訓となつたもの」とあります。そして、四世紀の郭璞が作つた辭書『爾雅注』からの引用が載せられてゐます。それを葉鍵得の著書から引いてみませう。(一)苦而爲快、(二)以臭爲香、(三)以徂爲存〈死・生〉、(四)以亂爲治、(五)以曩爲曏〈ひさしい・直ぐ前〉、(六)以故爲今
洋の東西を問はず、このやうな矛楯した、反論理的な言語の有り樣が既に千數百年も前から氣づかれていたことは驚異的です。ただ反語は對義語二つを「矛楯」とか「慇懃無禮」のやうに強引に結びつけたものであるのに、漢字の場合は一字に反對の意義が含まれてをり、矛と楯が一語の中に含まれてゐる漢字といふのは諸刃のやいばのごときもので、どちらから攻められるのか、空恐ろしい氣がしないでもありません。
『編集傍訊―異體字整理って何?(1)』――筆記體と活字の字體の違い
高崎一郎
突然ですが、仮に「a」の筆記體が「α」、「g」の筆記體が「ξ」だとしてみてください。
もし「a」と「α」が別々の文字だと言はれたらずいぶん不便ぢゃありませんか?
近頃では筆記體はあまり流行りませんが、それでも「a」や「g」をきちんとなぞって手書きする人は稀でせう。活字も「α」「ξ」で揃へよう、さうすれば簡單で科學的で民主的な新社會になるいふ考へ方は、まあ全然わからぬでもありません。 ただ、「a」と「α」とはどう考へても同じ文字。『戸籍によると貴方は「a」さんで、銀行通帳の「α」さんではありませんね。口座の預金はおろせません』と言はれたらびっくりしますね。少なくとも筆者自身は「高崎・髙﨑」の字體差が理由で、あちらこちらで銀行通帳を作り直しました。
しかも
・常用の單語は「α」「ξ」に改める。
・表に出てこない難しい單語は原則廢止の方向だが、當面は「a」「g」のままで書いてください。
なんて方針を戰後七十年、默々と守ってきた國民はじつに偉いものですな。
だって綴り方によって「αg」やら「aξ」やら組合せは増えるばかり、しかもそれらはすべて「異なる單語」に算へるらしい。
いっそ元のままがよかったと思ふのですが、學術調査によると「古い文獻で『ag』の印刷例は少なく、『aξ』こそ眞に傳統的な書體です」といふ結果が出たり、「そもそも『これが正しい』と決めつける態度がいけない」などなど議論百出。もう何が何だかわかりません。
そんなこんなで今、「異體字」は大いに注目されてゐます。ただし細部に蘊蓄をかたむけると、卻って全體がわからなくなります。理解の要諦はただ一つ。
「活字と手書きでは字體が異っても構はないのだ」といふ點にあると思ふのですが、如何なものでせうか。
『異體字整理に必要な時代や地域の視點』
――『基本漢字字形表』が目指すもの(4)
高崎一郎
「フォント指定」といへば「ゴシックで強調しよう」「年賀状を筆文字で印刷」といった場面が頭に浮ぶ。しかし異體字を表現する重要な手段でもある事はあまり認識されてゐない。「TrueType Font」の利用により、『今昔文字鏡』は十萬種類を越える漢字表現を實現してゐる。
たとへば「飮」と「飲」はJIS漢字の別々の場所に登録されてゐる。だから「コードポイント」つまりそれぞれの所番地を指定するだけで異體字を區別する事ができる。ところが「葛」には、下部が「匃」字形と「匂」字形の異體字が流通するものの、所番地は一つしかない。厄介な事に、使ってゐる機械によって前者の字體に見えたり後者であったりと一定しない。仕方ないので「筆文字で印刷する」のと同じ要領で「印字し分ける」のである。
實務上、これはあながち惡い方法とはいへない。異體字の數は際限がなく、また「飮・飲」や「煕・熙・熈・凞」のやうに微細な區別をつけるのが常に有意義とは限らないからである。「葛」の例が有名になったのも、「葛飾區(匃)」と「葛城市(匂)」二つの自治體で使ってゐた字體がそれぞれ異なってゐたといふ些細な理由であり、行政上の混亂がおきたわけではない。
つまり字體の問題を把握するには
・コードポイント
・フォント
の二段階の表現を理解する必要がある。たとへば英字でも「a」や「g」の手書きは相當に字體が異なるが、それでも「a」や「g」であると認識できる。そのやうな幅廣い文字概念がコードポイント、個々の具體的な書き方がフォントと考へればよいだらう。
もっとも前述の「飮」と「飲」などは恐らくフォント差とすべきだったのであらうが、早い段階で別々のコードポイントとして登録されてしまったので、もはや取り消すわけにはゆかない。英字よりも遙かにややこしいのである。
今囘の『基本漢字字形表』は、コードポイント指定として
・ユニコード番號
・JIS漢字第一~第四水準の別
またフォント指定は
・今昔文字鏡番號
を豫定してゐる。いづれも現時點で最も網羅的かつ普及した規格である。これに簡單な音訓をつけ、それがどのやうな字であるか明示する豫定である。「巳・已・己」などは紛れやすい字として、また「妛・仂」などはそもそも如何なる漢字か議論あるところだからである。
ちなみにJISコード漢字一覽といった資料に印刷されてゐる字體は「例示字形」といって、あくまでフォントの一つにすぎない。「a」が「b」に見えるフォントを作られては困るから、JIS規格では字體表現の幅が「包摂規準」で決められてゐる。だから「葛」の下部は「匃」でも「匂」でも規格に違反しない。「㈲申申閣」の假名漢字變換システム「契冲」に付屬する「文字鏡契冲」はこの表現の幅を利用して、普遍的な環境下で基本字形を表示させる努力を二十年前から續けてきた。
二十年前といへば未だワープロ專用機全盛の時代で、たとへば『般若心經』の入力でさへ標準的ならざる技巧をさまざま驅使したものだった。今や世界標準のユニコードはコードポイント數だけでも十萬種を越え、「無い漢字」を見つけるのが逆に困難である。それにもかかはらず日常の現場ではさまざまな不足を歎く聲が絶えない。上述の「葛飾區」と「葛城市」の區別など、フォントの操作に熟達した人以外は困惑して當然であらう。
漢字とはかくも面倒なものなのだらうか。
(1) 「匃」にせよ「匂」にせよ、同じ漢字構成部品「曷」である。
(2) 傳統的に印刷では「匃」、筆寫では「匂」字體が多かった。
といふ事に過ぎず、ややこしくなったのは
(3) 「当用漢字」で特定の漢字のみ、印刷でも「匂」が「正しい字體」とされた。
以降の事である。
(3)で採用された
・「喝・渇・掲・褐・謁」
などの「匂」字體に對し、對應する「匃」字體はユニコード上で
・「喝・渴・揭・褐・謁]
といふ別のコードポイントとして登録されてゐる。
そして(3)に含まれなかった
・「曷・蝎・鞨・葛・藹・臈」
などは全般的に「匃」優勢である。「葛」一字のみ環境によって「匂」になる可能性が高いため、正確を期すにはフォント指定が必須となる。
かくのごとく實務的整理をほどこせば、JISコードやユニコードに通曉しなくても漢字表現の幅はもっと廣げられる。 「当用漢字が惡い」「いや朝日文字が惡い」 などと批判するよりも、『基本漢字字形表』をよく煮詰めて「どうすれば惡くなくなるのか」を建設的に提示してゆきたい。
『異體字整理に必要な時代や地域の視點』
――『基本漢字字形表』が目指すもの(3)
高崎一郎
漢字表とは至って地味な存在である。『常用漢字表』を座右に置いて愛用する人はごく少數であらう。しかし平成二十二年の改訂時も「この字が入った消えた」と、隨分論議を呼んだ。しばらく經つと市販の辭書は揃って「新改訂の漢字表に完全對應」と、腰帶に特大の字を入れ始める。「漢字の負擔、また増加」なのかどうか知らないが、確かに世の中を靜かに、しかし大きく動かすのである。
個人が漢字表を作っても、他人が振り向いてくれなけば意味がない。ただ昔と違って、何事も共通化が大前提の時代になった。たとへ仲間内だけであらうと、例へば「煕・熙・熈・凞」のどれが標準的か確認しておくのは大いに意味があるし、また異體字と設定しておかなければ四文字それぞれ別々のデータとなり、關聯がわからない。特段の意圖がないにもかかはらず表現の幅が廣すぎるのは、明らかに不便なのである。
そんな用途など、すでに社會的に統一されてゐて間然するところがないと思はれるかもしれない。しかし事實はさうではないから「禱・祷」のどちらが正しいか議論になる。平成十二年『表外漢字字體表』は「禱・祷」の兩方とも認める一方で、「濤」はこの一字のみの掲載だから恐らく「涛」は駄目なのだらうと推測するいった不可思議な状態である。
上述の「煕・熙・熈・凞」は『表外漢字字體表』にもない。ただし法務省の人名漢字は「熙」である。左上部分は「姫」と違って、なぜか「臣」とは略してない。これは戸籍の用途に限る筈だから、たとへ人名であっても韓國の「朴正煕」大統領など康煕字典體によるのが通常である。しかし文部科學省では、精査したわけではないが「いわゆる康熙字典体」などの表現に人名漢字の「熙」を使ってゐた。世の趨勢に反してまでさう書くのはきっと何かの根據があるのだらうが、だんだん頭が痛くなってくる。
何も字體の細かい相違に目くじらを立ててゐるのではない。現代社会では書籍の入稿データも顧客名簿もデジタルで編輯するのが常である。「煕」と「熙」では文字のコードポイントが全く異るから、ひとたび扱ひを間違へるとどちらか一方の存在に全く氣づかないまま、索引の類が仕上がってしまふ危險性がある。
ただし『康煕字典』を盲信するのは考へものである。たとへば「査」は「查」とあり、中華圈ではむしろこの字の方が流通してゐる。しかし從前から字源上あきらかな誤字とされてをり、敢て「查」にこだはる意味は薄い。字體の歴史的變遷など、近年ますます精密に研究されるやうになり、傳統的とされてきた字體が「眞に傳統的」なのか、さまざま異義が唱へられるやうになった。つまり考證としては正しくても、現代の用途としての標準化は大いに損はれる事となった。
結局、長年の間に形成された「いはゆる康煕字典體」がやはり最も安定してゐる。また日本や中國で採用された略字はすべて「康煕字典體からの置き換へ」として定義されてゐる。しかし行政や實業や教育では現行の規範が絶對であるし、學術の世界では何事も實證的かつ批判的に扱ふ。「いはゆる康煕字典體」が單純な一覽表になったやうなものは意外に求めにくい。
今囘の「漢字表」編輯企畫の要點は此處にある。
『異體字整理に必要な時代や地域の視點』
――『基本漢字字形表』が目指すもの(2)
高崎一郎
まだ昭和の頃、異體字の社會的な話題といへば大抵は新字・舊字の對立であった。中國の簡體字と共通化しようといった提案や、逆に「輕薄な略字」を嫌って傳統的正字に戻さうとする動きは今でも跡切れたわけではない。
昭和二十一年の『当用漢字』は筆畫の單純な異體字を取上げ、標準字體を多く變更した。ほとんどは從來からある略字や俗字であったためよく定着したとも言はれるし、またこの種の國家的な強權が支持された時代でもあった。「固有名詞については別に考える」とはされてゐたものの、「濱崎さん」は當然「浜崎さん」であるべき風潮だった。
つまりそれは「異體字の排除」であった。戰後漢字政策のもう一つの柱は漢字制限で、こちらは如何にも窮屈だから早々に破綻した。さうなってみると同系統の漢字でも略字になるものとならぬものがあって不釣合だから、「涛(濤)」「祢(禰)」など新たな異體字が流通し始めた。擴張新字體または朝日新聞社の「朝日文字」などと呼ばれたものの、明らかに新字・舊字の路線對立の延長線であった。
固有名詞については「別に考える」事もなく平成の世を迎へたが、意外な形で解決を迫られる事となった。OA機器の普及につれ、定義しない漢字は相手にも讀んでもらへない事がわかってきたからである。「乢(たわ)」「萢(やち)」「湶(あはら)」など、必要だが注目されない漢字がどれほど種類があるか誰も知らなかったし、「そんなに難しければ改名か假名表記にせよ」などと迫れる時代ではすでになかった。
新字・舊字は限定的な設計思想の爭ひであったのに對し、あらゆる異體字について考慮しなければいけないといふ、質的に新しい段階に入ったのである。「濱崎さん」または「浜崎さん」しか認めない標準化絶對から、「濵﨑さん」も同居が可能な、緩やかな異體字の共存へと移り變った。ここ二十年ほどでさまざま實態調査も進み、漢字表現に關して深刻な問題はかなり減った。
もっとも少し昔の人なら「崎・﨑」の二字は書體の相違であって、異體字ではないと感じるかもしれない。印刷物は「崎」、書寫は「﨑」と無意識のうちに使ひ分けてゐたがゆゑ、全國の舊戸籍で「﨑」が非常に多く出現する。これらの實態を今の現實にどう反映すべきか、そこはさまざま解釋や運用があってよいだらう。
今、もっとも不足してゐるのがその系統的な解釋や運用である。漢籍などで裏づけられた共通理解も、昭和の終焉と共に期待できなくなった。前述のとほり当用漢字・常用漢字の範圍内外で、設計思想の異る字體が混在してゐる。また傳統的字體といっても、「澀・澁」「窗・窓」「兔・兎」「苺・莓」など評價の曖昧なものが案外多い。「並」でなく「竝」とすべきなら「椪」も追隨すべきか、「枠」と「椊」ではどうかなど、『基本漢字字形表』を通じて明確にしてゆきたい。
『異體字整理に必要な時代や地域の視點』
――『基本漢字字形表』が目指すもの(1)
高崎一郎
近ごろ異體字が再び注目されてゐる。背景にはOA機器の急速な發達と、それに伴ふ世界的な規格化標準化がある。
漢字は非能率と停滯の象徴であり、漢字制限とローマ字化こそ最有力の處方箋だ、そんな考へ方がほんの三十年ほど前まで少くなかった。ところが今や我々はあまりに多くの漢字を使へるやうになり、逆に少々持てあましてゐる。なぜ漢字はかくも數が多いのか。大部分は異體字による重複なのである。
異體字とは同音同義にして形の異なる漢字を指す。典型的な例では「國・国・圀」はそれぞれ異體字の關係にあり、「邦」はさうでないとされる。訓こそ同じ「くに」であっても字音「コク(國)」と「ハウ(邦)」は異なり、同一視はできないからである。
しかし一般的に異體字は「標準的ならざる字體」の意味で用ゐられる事が多い。つまり昔は「國」が標準だったから「国」や「圀」が異體字であった、しかしその後「国」が正式となったから、現在では「國」「圀」が該當するといふ受取りかたである。確かに考へ方の座標軸はあった方がよい。
異體字の關係は決して單純ではないからである。辭書によっては「囗」も「國」の異體字とするが、同時に「圍」の異體字でもあるといふ。「辨・辯・瓣」は現在いづれも「弁」となったが、では「辨・辯・瓣」が相互に異體字關係にあるわけではない。「着」は「著」から分化したが、現在では音訓共に全く別の漢字であるかのやうに振舞ってゐる。
さらに辭書によると「吊」は「弔」の分化、「陣」は「陳」の分化であるといふ。もし單純に「異體字はなるべく整理する」方針を立てたとしても、「着」「吊」「陣」を排除するわけにはゆかないだらう。「万」は「萬」の略字であると萬人に認められてゐる筈だが、「万さん」といふ姓の人は「ボクさん」と讀み、決して「萬さん」ではない。ただし身近に「万さん」の知合がゐる人は滅多にゐないだらう。
つまり異體字の整理にも、時代や地域の視點が必要なのである。「常用漢字表」の類は「この字が入った落ちた」「略字か正字か」などの話題ばかり盛んだが、じつは「着」「吊」「陣」を認めてゐるかどうかは異體字の認識に決定的に重要である。
現在廣く普及しつつあるユニコードは各種地域や新舊の系統が混在した「ごった煮」である。これを如何に解きほぐすか、分析は深化したが、萬人にわかりやすい明快な整理はまだ發展途上である。從來の漢字制限思想による切捨てや、規範主義による序列の爭ひが色あせてきたのは慶賀すべきではあるまいか。
『甲骨文字は神聖文字』
古家時雄
甲骨文字は商(殷)王朝時代に亀甲・獣骨を素材として彫穿した文字である。甲骨文字(甲骨亀甲文字)の名稱もここに由来する。
甲骨文は亀甲・獣骨などの素材に彫り刻まれ、神に開戦の有無や方法、豊作への祈願、王朝の行事、それらに善い神託をえるための犠牲の数など、善い神意を得るため用いられた。
甲骨文を表に彫り、裏面に小孔を穿(うが)ち、熱した青銅棒を孔に当てて加熱すると、卜の音ともに亀裂が入る。この亀裂が卜文で、神から人への託宣は、卜文を神官(貞人)が解釈することで明らかになる。これが商の占卜(龜卜(きぼく))の流れである。この神事には神官と王と王族の一部を含む限られた聖職者のみが占卜に携わることができた。善い神意を得られない場合は、犠牲などの条件を替えてを幾度も繰り返された。
神との文字による交信は、甲骨文で問い、卜文で神託を得るのだが、人との交信方法はどのようであったのだろうか。残念ながら、人と人の情報伝達に使われたことを証明する商王朝の出土物はない。商の金文遺物には一文字のみの使用が認められるものがある。これはトーテム的な意図で甲骨文字を合成させた部族名だろうと考察されている。文字は複数で使用して、初めて文と呼べる。夥しい甲骨文遺物のなかに、人から人へ伝達するために使用されたことを証明する文が全く存在しないことは驚きである。
商王朝末の一時期、周が商打倒を諸侯に協力要請するために甲骨文を用いた事例が唯一存在する。これが人と人の情報伝達の初めての事例である。周王朝に入ってからの文字遺物は、鼎(かなえ)や鬲などの銅器に記された金文遺物が主たるものとして發見されており、王朝から個人に対して軍事的な功績を顯彰する文などが多くあり、それらは人から人への意志通達のための文である。したがって、人から人への伝達に目的を変えた文字は周より始まったと考えてよい。周王朝以降の占卜は筮竹(ぜいちく)が主役となり、竹簡・木簡・玉簡などの出土遺物が発見されるが、甲骨文字が使用された出土物はまだない。
この文字の使用目的の変質は、文字に人の生活活動に根ざした意味を発生させ、甲骨文字5000字弱から文字数は増大していく。
たとえば甲骨文字で木と喬はあるが、橋は周以降の文字である。
甲骨文字の喬は雷神が高楼に降り立つ姿のようにみえる。天界と人界を繋ぐ橋といえよう。しかし「橋」は人が渡るための木製の橋に他ならない。
神のみを対象とする神具としての神聖な甲骨文字も、人が生活に文字を使えば思索の道具となる。言い換えれば、より高い文化を生み出すための土台ができあがったといえる。それは新しい概念の誕生を促すものであり、多種の思想が開花する素地となった時代である。まさに周王朝の誕生は文明が飛躍する歴史的転換点であり、我々の漢字使用の原点といえる。しかしながら、現在の夥しい漢字のなかから、甲骨文字と同一の意味を持つ文字が見いだせないことも心に留めておきたい。
下記の図は漢字「龍・竜」を甲骨文字に変換して一致するとおもわれる『甲骨文編』番号1378集合の一部。龍・竜に多くの甲骨文字が対応しているのが読み取れるが、龍・竜以外の文字である可能性も否定できない。しかし、現代の漢字にいたるまでに失われた文字の多いことも読み取れると思う。甲骨文の完全な解読には更なる出土遺物の発見が求められる。
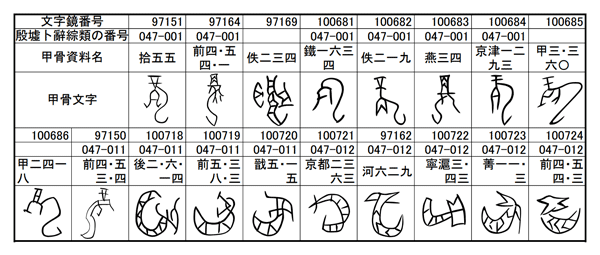
史記の「龜策列傳」によると、司馬遷は史記編纂のために龜卜について調査を行ったが、遂に發見することが叶わなかったと述べ、龜卜が国家の大事であったことを示す春秋時代の伝承を紹介している。このことから周時代以降も占卜の秘跡を保持する家が存続していたことが推察できるが、少なくとも前漢頃には伝承が途絶えてしまったのであろう。その後甲骨文字が歴史に登場することはなかった。1899年に至り、薬剤店で漢方薬の一種として発見されたが、本格的な学術研究は1928年からの殷墟発掘調査を待つことになる。(殷墟は商王朝の首都に比定されている)我國では龜卜は伝承されており、卜文の解釈も可能だが、甲骨文字を使用した遺物は発見されていない。戦後まもなく伊豆の洞窟で龜卜に用いた獣骨が發見されたなかに、甲骨文の「不」が刻まれたものが写真に撮られていたが、現在そのすべての出土物が紛失されているのが残念である。
【本稿は著者の許諾を得て、『外字異体字のバリアフリーを目指して』(文字文化協會刊)より転載した】